2019年10月28日、東京など一部地域でタクシーの「事前確定運賃」制度が正式にスタートしました。
一言でいえば「乗る前にタクシー料金が確定する」というものです。
渋滞に巻き込まれ、前に進まないのにメーターだけが上がっていくという苦い経験をお持ちの方なら「いいじゃん!」と思うところですが、実際のところ、通常のメーター運賃よりお得なのでしょうか?
私たちの結論は「かえって割高になる可能性が高い」です。
その他、細々した条件を考え合わせると、その地域でタクシーに乗り慣れている人には、あまり利用価値のないサービスだと考えます。
以下、そう考える根拠を示します。
目次
事前確定運賃とは?
まず、事前確定運賃とは何か、もう少し詳しく解説します。
到着まで確定しない「メーター運賃」
通常、日本のタクシーの運賃は乗車距離(+低速走行の時間)によって決まり、タクシー車内に備え付けのメーターで運賃をカウントします。
ですから、目的地に着くまで正確な運賃は分かりません。
スタートとゴールが同じでも、経路が違えば運賃は違ってきます。
経路が同じでも、信号待ちや渋滞によって運賃が上下します。
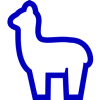
ここまでは、タクシーに乗ったことのある人なら「何を今さら」という話ですよね
不安だからタクシーに乗らない人がいる?
しかし、「乗る際に正確な運賃が分からない」ということが不安だからタクシーに乗らないという人も一定数いる、らしいです。
確かに、電車やバスなら乗る前に運賃が分かりますから、「そんなに高いなら乗らない」といった判断ができます。
また、目的地に到着してから「あと500円ください」と言われるようなこともありません。
それに比べて、タクシーは「何が起こるか分からない、だから心配」というわけです。
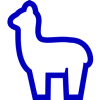
ずいぶん臆病だなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、自分が海外に行ったときのことを考えると、多少はその気持ちが分かるのではないでしょうか
アプリ利用で、乗る前に運賃が決まる
そういった背景のもと、国土交通省では数年前から「事前確定運賃」の実証実験を進め、2019年10月に本導入となりました。
事前確定運賃では、スマートフォンのアプリを利用することが大前提となっています。
まず、利用者はアプリで「スタート」と「ゴール」を入力します。
すると経路と運賃が表示されます。原則として2つ以上の経路が示されるようで、経路により運賃は異なります。
利用者が経路と運賃を承諾すればタクシーが来て、表示された運賃で乗車できる、という流れです。
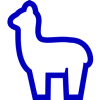
迎車が暗黙の前提となっています
外国人旅行者など、地理に不案内な人でも、事前に運賃が分かることで安心してタクシーを利用できるようになる、というのが国土交通省の狙いです。
事前確定運賃はどう決まる?
利用者として、選択肢が増えたことはひとまず歓迎です。
その上で、実際にこれを利用するかどうかと考えたとき、まず気になるのは「メーター運賃と比べて、事前確定運賃は高いのか?安いのか?」というところだと思います。
これに答えを出すには、事前確定運賃の算出方法を知っておく必要があります。
実は、事前確定運賃の算出方法は厳密に決まっており、国土交通省が算出方法を広く一般に公開しています。
これを読み解きながら、事前確定運賃の仕組みについて見ていきます。
本来は「損得なし」
まず「そもそも論」として、事前確定運賃は割引や割増を意図したものではありません。
タクシーの運賃は、不当に高くないか(安くないか)といったことを勘案の上、各タクシー会社が申請した運賃を国土交通省が認可し、あるいは国土交通省が「公定幅運賃」を指定しています。
つまり、お役所的には、従来の(事前確定でない)通常運賃が適正であるということです。
事前確定運賃は、あくまで事前に運賃を決めることが目的ですから、「適正な」通常のタクシー運賃と平均的には同額にしたい、というのが国土交通省の考えです。
ですから、事前確定運賃はお得なのか?と問われれば、「平均的には損も得もしない」という答えになる、はずです。
渋滞や信号待ちを時間帯ごとに「係数化」
国土交通省はタクシー会社からデータを集め、「○曜日の×時台の△地区の渋滞・信号待ちはこの程度」という「係数」を決めました。
タクシー運賃は乗車距離によって決まりますが、一般道を走行する際は、10km/h以下の低速走行時に「1分40秒あたり80円」のような加算が行われるのがふつうです。
これを「時間距離併用運賃」と呼び、「下車するまでタクシー運賃が決まらない」という現象の大きな理由はこれです。
東京23区の一般的なタクシー会社の場合、渋滞や信号待ちが全くなかったとして、3km乗車時の通常運賃は1140円です。
しかし実際には、渋滞や信号待ちで10km/h以下の低速走行が発生し、運賃はこれより高くなることがほとんどです。
たとえば3km乗車時の実際の運賃が1300円だったとすると、これは「距離だけから算出した運賃」の(1300÷1140=)1.14倍ということになります。
この「1.14倍」のことを、以下では「係数」と呼んでいます。
国土交通省は、「何曜日の何時ごろ、何km乗車時に運賃が何円」というデータを集め、1乗車ごとに係数を算出し、それらを曜日・時間帯ごとに平均して「○曜日の×時台の△地区の係数は1.14」といった表にまとめた、ということです。
一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃算定に用いる係数について
(関東運輸局)
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/taxi_jigyoukaisi/date/kakutei_keisuu.pdf
表を開いて見るのが面倒だという方のためにざっくり解説すると、縦軸に曜日、横軸に時間帯(0時台、1時台、…、23時台)という表が営業圏(たとえば東京都心であれば「23区+武蔵野市+三鷹市」)ごとに1つ掲載されています。
係数はおおむね1.1~1.4の範囲に収まっています。
会社間で運賃に差はない
各タクシー会社はこの係数を使って事前確定運賃を算出することになっています。
つまり、ベースとなる通常運賃が同じならば、どのタクシー会社でも事前確定運賃は同額となります。
実証実験段階では、参加する4社がそれぞれ独自の算出方法で事前確定運賃を算出していたため、会社間で相当な差があったようですが、今後、そのような現象は原理的にあり得ません。
事前確定運賃が明らかに不利になる場合とは?
ここまで読んでいただいた方は、事前確定運賃は通常運賃に比べ明らかな損得はない…と理解されたかと思います。
しかし、あくまで「平均すれば通常運賃と同じ」というだけですので、実際には、多くの場合に損得が出ます。
そして、損得は宝くじのようにランダムに発生するわけではなく、「こんな場合は損」などとある程度事前に予測できます。
計算方法からして、乗降地や経路によって「明らかに損」という事例があります。
逆に「明らかに得」という事例は少ないように思います。
事前確定運賃の「係数」を眺めながら、具体的な損得について考えます。
事前確定運賃では何が考慮される?
タクシーに少し詳しい方なら、以下のようなことはご存じかと思います。(以下は東京23区の一般的なタクシー会社の例です。)
- タクシーを呼ぶと迎車料金がかかる
- 時間距離併用運賃は、高速道路を走行中は適用されない(高速道路で渋滞してもメーターは上がらない)
- 深夜(22時~翌5時)は運賃が2割増になる
- 遠距離割引がある(9000円を超えた部分が1割引)
- 障害者手帳を呈示すると運賃が1割引になる
事前確定運賃では、これらはどう取り扱われるのでしょうか?
結論からいえば、上記5点の中で「高速道路走行」については、事前確定運賃では全く考慮されません。
逆に他の4点については、通常のメーター運賃と同じです。
迎車料金がかかる一方、遠距離割引、障害者割引も適用になります。
深夜割増は係数に反映されている
補足しておきたいのは深夜割増です。
深夜の割増運賃は、事前確定運賃では係数に反映されています。
通常のメーター運賃だと、22時から翌5時の間は距離のカウントが2割増しになります。
たとえば1km走行した場合、メーターが1.2km分進むということです。
事前確定運賃の場合、メーターで距離を測るということをしない代わり、深夜は事前に運賃を2割増したものが乗客に提示されます。
「高速」モードはあっさり無視!
一方、事前確定運賃であっさり無視されてしまっているのが高速道路走行時の取り扱いです。
高速道路を走行中は、運転手がメーターを「高速」モードにします。
この操作をすることによって、「時間距離併用運賃」の適用が止まります。つまり、渋滞で完全に停車しているのにメーターだけ上がっていくという、あの現象が起きなくなるわけです。
しかし事前確定運賃では、提示されるルートに高速道路が含まれても係数が変わることはありません。
元々、事前確定運賃の係数は「信号待ちや渋滞による増額分」、言い換えれば「時間制運賃による増額分」を示した数値と考えられます。
それなのに、一般道経由でも高速経由でも同じ係数が適用されるのですから、高速道路を利用する経路では、事前確定運賃は明らかに大損です。
信号待ちも渋滞もなければ絶対に損をする
この問題は高速道路に限りません。
郊外によくある、信号の少ないバイパスでも似たようなことがいえます。
繰り返しになりますが、事前確定運賃の係数は、信号待ちや渋滞によるロス(運賃の増加)を平均した値です。
であれば、信号待ちや渋滞のほとんどない経路で事前確定運賃を利用すると、まず間違いなく損をします。
事前確定運賃は都心向き?
事前確定運賃は、渋滞や信号待ちが少ないと分かっている場合に損だということがお分かりいただけたかと思います。
では逆に、多少の渋滞が予測される場合には、事前確定運賃のほうがお得になるでしょうか?
私たちの実体験に基づいた「タクシー感覚」からいうと、郊外の道路を走る場合には、得になることはあまりなさそうです。
昼間の都心の小移動のように、走行時間に比して信号待ちの時間が長い乗車ならば、多少は得になる場面があるのかなと想像します。
係数「1.3」は相当な渋滞だ
実は私たちは、事前確定運賃の制度がスタートするずっと以前から、タクシーに乗るたびに「係数」を計算し、データを蓄積していました。
自宅が「特別区・武三交通圏」の端のほうにあるので、「郊外~都心」あるいは「郊外~郊外」の利用が多いのですが、少なくとも郊外を含む乗車で、係数が1.3以上になることはなかなかない、というのが実感です。
たとえば自宅から都心の大学病院まで、休日のお昼時など、道が混んでいなければ1時間弱で着きます。
この場合の割増率は10%台前半、つまり係数でいうと1.15弱です。
これが平日の朝方だと1時間20分以上かかることがあり、運賃もその分高くなるのですが、それでも係数が1.3以上になることは稀でした。
体感として、深夜など極端に空いていると1.05程度、通常の時間帯で最初から最後までスムーズだと1.1程度、ところどころ流れが悪いと感じれば1.2程度で、係数が1.3に達するのは、最初から最後まで流れが悪いような場合に限られます。
平日昼間の係数は軒並み1.2超え
一方で国土交通省が定めている係数を眺めると、平日昼間の係数はほとんどの場合に1.2を超えています。
たとえば東京23区の水曜日の係数を見ると、朝8時台に1.24となり、そのまま21時台まで1.2以上をキープします。22時台からは深夜割増が入って1.3台となります。
逆にいうと、1.2未満となるのは朝5時台~7時台だけです。
都心の短距離利用ならお得か
以上のとおり、少なくとも東京23区の郊外を含む乗車では、設定されている係数は割高感があります。
しかし、この係数は種々の乗車の平均値から算出しているので、郊外で事前確定運賃が損なのであれば、どこかに「事前確定運賃のほうが得になる乗車」というのがあるはずなのです。
それが何かと考えると、消去法で「都心部の短距離利用」ではないかと思います。
そうした乗車に関しては、事前確定運賃を選択することで、メーター運賃より割安になることがありそうです。
ただ、元々の係数が1.2~1.3と高めですし、短距離なら絶対的な運賃が安いため、劇的に安くなることはないと思われます。
郊外→都心、朝7時台は穴場か?
あと1点、表を眺めていて「おやっ」と思ったのが朝7時台です。
23区の場合、昼間の係数は軒並み1.2超えなのですが、朝7時台は火曜と木曜が1.19~1.20と低めになっています。
7時台だと、都心の交通量はまだ少ない一方、郊外だと自動車通勤の人が多いせいか、7時半前後から、特に上り線が激しい渋滞になる傾向にあります。
郊外から都心へ向かう場合、係数が1.2ならば、事前確定運賃のほうが安くなる可能性があるように思います。
実は全然安心じゃない!? 事前確定運賃の謎ルール
以上、事前確定運賃の損得について詳細に見てきました。
「こういう場合には得になりそうだ」という気付きを得られた方もいらっしゃると思います。
そうでなくても、制度本来の目的である「運賃が先に決まって安心」ということにメリットを感じられた方もいらっしゃるでしょう。
しかし!
事前確定運賃には、メーター運賃にはない不安材料があるのです。
私たちは、これを見て「極力、利用しないぞ」という結論に至ってしまいました。
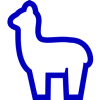
改善してほしい!という気持ちをこめて、この注意点をご紹介します
乗車中に目的地を変更すると大損!
その注意点とは、乗車中に目的地を変更した場合の扱いです。
たとえば、事前確定運賃を選択して自宅から病院に向かっている途中、急に呼び出しを食らって行き先を学校へ変更…ありそうな話ですよね。
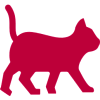
これウチの話でしょ。本当にありそうで怖い
このような場合、変更を申し出た時点で病院までの事前確定運賃を全額支払い、あらためて、その地点から通常のメーター運賃で学校へ走り出すことになります。
以上の文をスーッと読んでしまった方。よーく考えてください。
たとえば病院までの事前確定運賃が8000円だとします。
自宅を出て、5分ぐらい走ったところで行き先を学校に変更します。
すると、5分しか乗っていないのに8000円を支払い、さらにそこから学校までのメーター運賃を追加で支払うのですよ!
要するに前払いみたいなもので、一旦走り出したら事前確定運賃は全く返ってこない、キャンセル料100%だと理解すればよいでしょう。
国土交通省がこう決めた
間違いではないか?あるいは、こうは書いているけど実際にはオマケがあるのではないか?とよくよく調べたところ、そもそも国土交通省が「こういうルールにしなさい」と決めていることが判明しました。
今回の事前確定運賃についての詳細を定めた文書として「一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃に関する認可申請の取扱いについて(平成31年4月26日 国自旅第31号)」というものがあるのですが、これによると、事前確定運賃の要件として以下のようなことが定められています。
運送途中で旅客の都合によって走行予定ルートの変更(やむを得ないものと事業者が判断した場合における走行予定ルート上の施設への必要最小限度の時間内での立ち寄りは含まない。以下同じ。)を行う場合には、事前確定運賃による運送をその時点で終了し、事前確定運賃額を収受するとともに、新たに当該運送終了地点から距離制運賃により運送を開始することとする。
監督官庁に言われたのでは仕方ありません。
事前確定運賃を採用しているすべてのタクシー会社で、このルールが適用されます。
従来の「定額」となぜ違う?
今まで、降りる前に運賃が決まるサービスとしては「定額運賃」がありました。
たとえば東京23区だと「羽田定額」「成田定額」などがあります。
このような定額運賃で、乗っている途中に行き先を変更した場合、どういう扱いになるかご存じでしょうか?
実は、定額運賃を支払う必要はありません。
出発地から実際の(変更後の)目的地までのメーター運賃を支払えばよい、というルールになっています。
Q6 途中下車、行き先の途中変更、ルート変更などの場合、定額運賃はどうなりますか?
A6 お客様の都合による運行の中断、目的地の変更、予定した経路以外の経由等で定額運賃の目的地と「大きくかけ離れる」場合は、通常のメーター運賃となります。
今回もこのようなルールにすればよかったのに、なぜ「キャンセル料100%」のような厳しいルールにしたのでしょうか。
理由として1つ考えられるのは、乗客の「悪知恵」防止です。
実際に走り出してみたら、道が空いていてメーター運賃が意外に安く、事前確定運賃が割高であることが判明した…ありそうな話です。
こんなとき、わざと目的地を少しだけ変更し、事前確定運賃の適用を逃れようとする乗客が、出てこないとも限りません。
タクシー会社に有利すぎないか?
それにしても、利用者からすれば、何とかなりませんかというルールです。
事前確定運賃は割引や割増を意図したものではない、つまり利用者にとって金銭的なメリットは(平均的には)ない、ということは先に触れました。
裏を返せば、タクシー会社にとっても、事前確定運賃は有利でも不利でもない中立な制度であるべきです。
メーター運賃であれば降車するまで目的地を変更し放題であるところ、事前確定運賃の場合だけ「乗車開始時点でキャンセル不可、全額支払い確定」となるのは、タクシー会社に対し過度に有利な制度ではないかと思います。
私たちの感覚では、「行き先を変えたら全額返ってこない」というデメリットは、「事前に運賃が決まって安心」というメリットを大きく上回っています。
実際にこのルールで運用すると、乗客にとってあまりに不利である上、十分に注意喚起されているとは言い難く(小さい字では書いてあるのでしょうが)、トラブルになる例も少なからずあるのではないかと想像します。
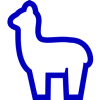
今後、改善されることを強く希望します
経路が選べない→玄人には向きません
最後にもう一つ、私たちが事前確定運賃を利用しない大きな理由を挙げておきます。
私たちの知る限り、事前確定運賃に対応したタクシーアプリは、スタートとゴールを入力すると、間の経路を「自動的に」提示してきます。
提示してきた経路が「自分たちの思い描く(最適な)経路」でなかった場合、事前確定運賃が割高になってしまう可能性が大です。
自分好みのルートが出てこない
たとえば自宅から病院まで、定期的にタクシーを利用している方の多くは、「この道が空いている」「ここを曲がると近道」といった、自分なりの最適ルートを把握していると思います。
しかし事前確定運賃に対応したアプリは、そこまで賢くありません。
「その道は遠回りだから通らないよな」といった経路を候補に挙げてきます。
そして、事前確定運賃は、その「遠回りしたときの距離」によって決まってしまいます。
ですから、運良く「自分の思っていたルート」が提示されれば別として、そうでない場合には、事前確定運賃を利用すると相当割高になってしまう可能性が、かなりあります。
ドライバーの知恵も運賃に反映されない
事前確定運賃であっても、たとえば事故があって渋滞がひどい場合、あるいはドライバーが「こっちの道のほうが早く着く」と思った場合、ドライバーの判断により、経路を変更することが認められています。
しかし、あくまで「事前確定運賃」ですから、ドライバーの判断でより近道をしたとしても、運賃は変わりません(安くなりません)。
所詮は「慣れてない人」向けのサービス?
こういう点だけ見ても、事前確定運賃はあくまで「その土地のタクシーに不慣れな人」のためのサービスでしかない、と思います。
道はよく知らないから、細かいことは言わない。
相場より1割、2割高くても、もともと相場観がないので文句はない。
先に運賃を提示してもらえる安心感には代えられない。
そういう人向けのサービスだというのは知っていましたが、実質的にはそういう人以外には活用できないという印象を強く受けました。
タクシー運転手に道案内できるような技量を持った人は、事前確定運賃を利用しても不満が募るばかりです。
実は前からあった、実質的な事前確定運賃
実は、事前にタクシー運賃が確定して安心、というサービスは以前からありました。
トランが運営するサイト「らくらくタクシー」です。
実態は「予約制の事前確定運賃」
トップページに「定額制」「定額料金」と謳っており、確かに「空港定額」のようなサービスもあるのですが、ここで紹介したいのは、任意の2地点間のタクシー運送を予約するサービスです。
詳しいサービス内容は別のページにまとめましたので、興味があればご覧いただきたいのですが、運賃が事前に確定するだけでなく、通常運賃より割安になることが多いのが特徴です。

予約が必須なので、今回の事前確定運賃と単純に比較はできませんが、こちらのサービスを知っていると、事前確定運賃の「残念さ」をより一層強く感じます。
まとめ:せっかくの取り組みだから、細かな改善を
以上、周到な準備を経て導入された、タクシーの事前確定運賃について詳細に見てきました。
「割引や割増を意図したサービスではない」という大前提は分かりますし、確かにそのような運賃設定にはなっているのですが、日常的にタクシーを利用している人からすると、リスクが大きいわりに得るものが少なく、普段使いするサービスではないというのが私たちの出した結論です。
最初から旅行者向けを意図したサービスだということなのかもしれませんが、それにしても、乗車中の目的地変更は利用者にとって明らかに不利なルールであり、何が「安心」だよと思ってしまいます。
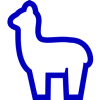
現場ではトラブルもあると思います。客からの苦情を受ける運転手さんは大変じゃないかな…
ただでさえタクシー会社側にシステムなどの投資が必要であるところ、トラブル事例がタクシー業界で共有されれば、新たに事前確定運賃を導入しようというタクシー会社はなかなか増えないのではないでしょうか。
今後、サービス内容の細かなアップデートを期待したいと思います。

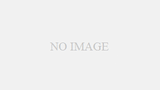
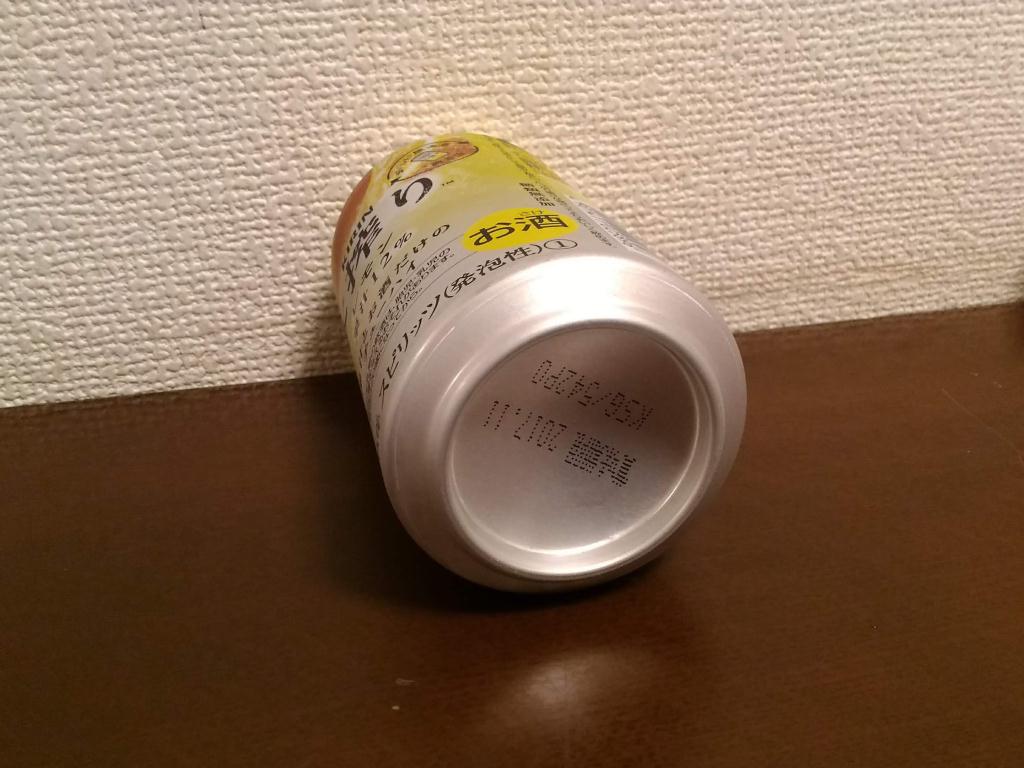
コメント